| 上田博章 「疎開絵日記」という本を出したのをきっかけに、ホームページを開きました。 私は平成天皇と同い年・同じ学年ですから、「太平洋戦争」が始まったのは国民学校二年生 のときということになります。この戦争は六年生の夏休みまで続きました。 「疎開絵日記」は、当時の子供たちが体験した戦時中の一時期を、正直に証言した本です。 とは言ってもこの証言は、戦争のほんの一断面にしか過ぎません。 しかし「戦時中に子供が書いた絵日記」という動かぬ証拠をネタに、シコシコ綴っていった記録です から、ハッタリや正当化、衒いやエエカッコを、極力排除した戦争体験記です。 子供の頃の拙い絵が挿入されはいますが「画集」ではありません。 ありきたりの「自分史」でもない…敢えて言えば、「子供の目で見た戦争の記録」といったところでしょうか。 1933年生まれの私たちは、「昭和天皇は現人神(アラヒトガミ=生き神様)だ」と教えられ、それを信じて戦争 の片棒を担いできた世代です。今にして思えば「けったいな世の中」でしたが、生まれた時からそんな環境 だったこともあって、それが当たり前だと思っていました。 例えば戦時中、周りの大人たちはこんなことを言っていたのです。 『敵地ニューヨークに特攻隊が突っ込んで、あの摩天楼をダーっと薙ぎ払ったらどんなに気持ちがいいだろう』 小学生だった私はナルホドと感心し、摩天楼という大人が使う難しい言葉を、そのとき覚えたものです。 それから57年経った2001年、ニューヨークの摩天楼が、体当たり攻撃によって崩壊してゆく姿を、茶の間で 見たときのショック…そうです、私たちは半世紀前はアルカイダだったのです。 戦時中のことを書き残しておかなければ…と思ったのはその時でした。 太平洋戦争末期に、子供たちが戦火を避けて地方へ移動した国家プロジェクトのことを、「疎開」といいました。 1943年当時、陸軍省の防衛課長だった父が企画立案したのが、この疎開制度でした。 とりわけ、子供たちを学校ぐるみで疎開させる「集団疎開」の法案については、東條英機総理に強く反対され ながら密かに推し進めた経緯があります。 ヨーロッパでの諜報勤務が長かった父は、ナチによる空爆を体験しました。 そんな無差別爆撃 から子供を守るために推し進めた国家的施策…それが学童疎開だったのです。 私たち学童疎開世代は、戦地で銃をとった経験はありませんが、爆弾や焼夷弾の下を逃げまどったり、 無差別爆撃から身を守るため親もとを離れて暮らしたり、空腹を抱えて勤労奉仕に汗を流したり… そういうことは体験しました。 まあ、この程度のヤワな戦争体験しかない私たちですが、そんな私でも「近ごろ戦争体験が風化したな」 と痛感するようになりました。 戦争を知らない総理大臣。無差別爆撃を、テレビ画面でしか感じたことのない有権者。 北朝鮮の攻撃を抑止するため核装備を主張する有識者…。 戦時中、「愛する家族や美しい国土を守るために命を賭けよう」と扇動していた当時の支配者 や、軍需産業を中心とする財界人の多くは、自ら前線に出ることなく、子息に赤紙が来ることも なく、戦争に負けたあとも生き続けました。 今の政治家や財界人にも、そんな狡さがほの見えて仕方がありません。 「昔陸軍、今財界」…戦後、よく耳にした言葉ですが、これはどうも眉唾ものです。 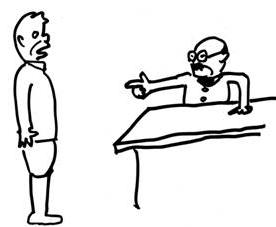 私の知る限りでは、戦時中でも財界が陸軍を支配していたフシがあります。 1944年(昭和19年)、建物の強制疎開(空襲に備えた建物の取り壊し)の責任者だった父が早朝、 東條英機総理に呼び出され、「小石川に在る財界人の別荘を計画路線から外せ」と命令されています。 父は総理の言うことを聞いて手直しをしました。ご近所の他の家が割りを喰ったそうです。 申し訳ない話です。そういえば、財界人の子息に赤紙が来たという話もあまり聞いたことがありません。 私よりほんのちょっと年長のお兄さんたちが、雨の神宮外苑で行進している記録フィルムを見るたびに 鼻の奥がツーンとなります。歓呼の声に送られて駅頭で敬礼をしている出征兵士の凛々しい姿、 無言館に展示されている画学生の作品の数々…、 こういう映像を、すごく身近に感じてしまうのが、私たち 疎開世代なのではないでしょうか。 世の中には「やってみないと判らない」リスクが多々あります。しかし、戦争だけは「やってしまったら 何もかもお終い」です。 キナ臭い世の中になってきました。戦争を知らない政治家や官僚が、日本を支配するようなご時世です。 私たちは、あの忌まわしい戦争体験に目を背けることなく、戦争の残酷さや理不尽さ、アホらしさを訴え続け、 あとは投票行動によって、孫たちを戦場に駆り出そうとする政治家に「ノー」の意思表示をしなければなりますまい。 2003年2月 |
HOME