←過去の記事を見る HOME 滑 舌(かつぜつ) 50年もの間、通勤は勿論、何処かへ行くときは、必ず阪急電車のお世話に なっています。 或る日、電車の中で突然怒声や、女性の金切り声が聞こえてきてビックリ したことがありました。 暴力団の喧嘩か、女の子が襲われたのかと思ったら、何と若い乗務員が、 あらん限りの大声を張り上げて、 「○○ よしッ!」 「出発 進行ッ!」 運転士や車掌の新人が、先輩の指導員に命じられてか「喚呼」をマニュアル 通りに…それ、も恥ずかしいほどの大声で、叫んでいたのです。 近ごろ、阪急電鉄は女性の運転士や車掌を乗務させていますので若い娘の 絶叫も車内に響きわたることもありました。 私は心の中で呟くのです。 「ビックリするがな。…けど、大声は最初だけやろな」 * 電車の乗務員は、乗客の生命を預かる重要な仕事です。 「喚呼」を恥ずかしがったり、照れたりせずに発音しなければなりません。 だからといって、あんなバカでかい声で叫ぶ必要が、どこにあるのでしょうか。 新人教育が終わったあと、ずーっと大声で叫ぶ乗務員など一人もいません… そんな現実は、指導する側も充分ご承知のはずです。 なのに、大声や金切り声を要求するのは、新入社員に「活」を入れ、恥ずかしさ、 照れ臭さを払拭₍ふっしょく₎するための伝統行事だとは思いますが、喚呼訓練で発する 大音声₍だいおんじょう₎は、客をビックリさせる「騒音」以外の何ものでもないと 私は思うのですが…。 * 実は よく似た伝統が、「アナウンサー業界」にも あったのです。 「口を正しく忠実に動かすことによって発声の基礎が築かれるのである」 昭和の初期から、NHKの先達アナウンサーが唱えてきた基本理念です。 これは多分、ラヂオしかなかった時代に確立された「局アナ教育」の伝統 ではなかったでしょうか。 テレビだったら、言葉が多少解り辛くても映像や字幕が助けてくれますが、 ラジオではアナウンサーの喋った言葉を、それも1回聞いただけで、解って もらう必要があります。 耳の遠い人でも、騒音の中で聴いている人でも解るアナウンスが肝要で、 魅力、テンポ、迫力などは、二の次三の次でした。 当時は、ラジオ受信機の性能が悪く、特に音質が良くなかったので、 「多少、口を歪₍ゆが₎めようが眼を剥こうが、ゆっくり、はっきり喋りなさい」 と 言われていたのかもしれません。 私が局アナになったのは1950年代でしたから、ベテランのアナウンサーは 皆さん ラジオで活躍してきた人が多かったからか、癖のあるケッタイな 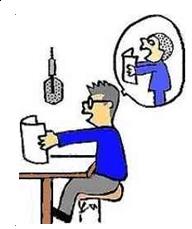 動きをする人がいたのです。 『いつもは普通に喋るのにマイクの前だと、 口を捏₍こ₎ね回さないとまわ喋れない人』 『文章の切れ目ごとに顎をグイッと、しゃくる人。 『舌なめずりを頻繁に繰り返す人。 『ニュースを読むとき必ず首をかしげる人』 『小学校で国語の教科書を読むときのように 原稿を立てる癖のある人』 …ラジオだと何ら問題ない動きですが…そんな人はテレビ時代に入って 神経を使っていました。 そもそ「局アナ」なんて所詮はサラリーマンです。 入社すると先ず同期のお仲間と一緒に社員教育を受けるのですが、局アナは 更なる訓練を受けなければならない…… 列車やバスの乗務員と同じでした。 ですから、新しく入ったアナウンサーがテレビやラジオでデビューするのは 五月か六月になるのです。 訓練を受けた新人アナが、初めて声を発することを、業界では「初鳴き」と 言っていました。 「初鳴き」の佳き日、スタジオの中に先輩アナが後見人として入ります。 「儂が居るから安心せえ」 と言わんばかりですが、人によっては安心どころか 却って緊張してしまうかも 知れませんけど…。 「初鳴き」の季節になると、あちこちの放送局で、妙な鳴き方をする新人アナが テレビ画面に姿を現します。 唇を捏ね回し、顔面神経を総動員してニュースを読む新人アナを見たことがある でしょう? 私は心の中で呟くのです。 「そないせんと、日本語が喋れんのかいな。ヘタクソ」 * NHKのアナウンサーで、大阪勤務のころ親しかったWさんが、高校生を 相手に発音を教えるテレビ番組で、こう言っていました。 「いいですかァ…アイウエオの[ア]は、指が2本入るくらい口を大きく 開けるんですよ」  …と言いなら指を2本くわえて見せたと思ったら、今度はヒョットコよろしく 口を尖がらせました。 「これが[ウ]の口構えです」 と指導していたのです。 ここで、ちょっと考えてみて下さい。 貴方が普段 喋っていて[ウ]や[オ]が出てきたときヒョットコみたいに 口を尖らせたりしますか? また日常会話中で[ア]という音を発するとき指がタテに 2本も入るほど 大口を開けたりしますか? 日本語はそんなご大層な口構えをしないでも話せる滑らかな言語なのです。 新人アナの訓練も、近頃でこそ、かなり改善されていますが以前は、何処の 放送局でも日常語とはかけ離れた滑舌を新人に押しつけていました。 「初鳴き」の新人が、口を捏ね回すのはその後遺症なのです。 しかし、これは一時的な症状で 一人前の局アナになれば普通に戻りました。 …阪急の運転士や車掌さんと 全く同じ現象です。 私が若いころ、上司に対して、 「どうせ元に戻るんだから、 妙な滑舌指導は不要です」 …なんて文句を言ったものですが、伝統とはなかなか破れないもので、 結局、 「上田は何でも反対しよる」 と先輩諸氏の反感を買うばかりでした。 * 入社して何十年か経つと、誰しも古株になってきます。 「何でも反対」の上田にも、採用試験の審査とか、新人教育 といったお役が 回って来るようになりました。 局アナの入社試験では、書類選考からマイクテスト、カメラテスト、筆記試験、 面接など 幾重にも関門を設けていますので、顔面を引つらせ、唇をゆがめたり しないで、スンナリ喋れる学生を採用すればよろしい。 多くの私大には放送部やアナウンス研究会があって、既に局アナになっている 先輩が 足を運んで、指導に当たっていました。 ですから、そこで訓練を受けた学生が、入社試験で優位に立つのは当然です。 そういう学生を、即戦力として採るかリスク承知で潜在能力に賭けてみるか…、 採用側は迷うのでした。 * 「かつぜつ」の漢字は「滑舌」、「活舌」…⋄どちらでもいいのだそうです。 「滑舌」は 元々、業界用語で、私が入社早々、教科書として使っていた 1956年発行の「NHKアナウンス読本」では「早口言葉」や「口の運動」 というのは出ていましたが、「滑舌」という言葉は入っていませんでした。 ところが、それから40年ほど経過した1978年「ABCアナウンス読本」 と銘打った朝日放送自前の教科書を作り、新人アナの教育に使ってきました。 の教科書には「滑舌」という言葉が出ています。 しかし「ABC読本」は朝日放送が「内向け」に出版したもので公の刊行物 とは違いますから、これだけで「活舌の由来」を云々するのは無理でしょう。 * 電子辞書や 比較的 新しい辞書で「かつぜつ」を引いて ワードで叩いても、 「滑舌」は出て来ますが、我家にある1993年の「広辞苑」には、「滑舌」 なんて出ていません。 手許にある1998年版の「NHKアクセント辞典」で引いても「滑舌」 は載っていませんでした。 どうやら「滑舌」という言葉は、思いの外 新しい業界用語だったようです。 「口の運動」よりは「滑舌」の方が使い勝手が良いからか、今や、日本中で 使われる日常語となりました。 * 「滑舌」といえば、安倍首相の滑舌は良くありませんなあ。 時々「酒乱的 自衛権」と聞こえることもありますし「思います」というのは どう聞いても「オメマス」としか聞き取れませんもの。 「四月」かと思ったら実は「七月」だったこともあるし、「みんな死んだかい」 なんて言われて愕然としたものの、よく考えたら「南シナ海」だったりして…。 私ゃ、耳が遠くなってきたのかな。 (徳島エコノミージャーナル 2015年6月号) HOME |